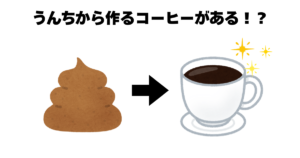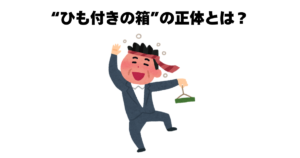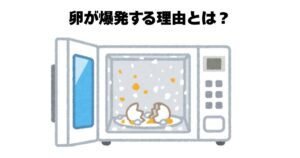日本の洋食メニューの定番「ハヤシライス」。とろっとしたデミグラスソースに牛肉や玉ねぎがたっぷり入った、あの甘辛い味わいがたまらない一皿です。でも、ふと疑問に思いませんか?
「ハヤシ」って誰?何?なぜ“ハヤシ”なの?
この記事では、ハヤシライスの名前の由来にまつわる3つの有力説と、よく似た料理「ビーフシチュー」との違いもご紹介。
この雑学を要約すると
- ハヤシライスの「ハヤシ」は、早矢仕 有的(はやし ゆうてき)という人物名に由来する説が有力!
- 「ハッシュドビーフ説」や「語呂合わせ説」など、複数の説が存在する
- ビーフシチューとは具材・調理法・食べ方に違いがある
ハヤシライスってどんな料理?
ハヤシライスは、牛肉や玉ねぎなどを炒めて、デミグラスソースやトマトソースで煮込み、ご飯にかけて食べる洋風の料理です。明治時代以降、西洋の食文化が日本に入ってきた際に登場し、今では家庭の定番料理となっています。
「ハヤシ」の名前の由来には諸説あり!
有力説①:「ハヤシさん」説(人名由来)
最も有名なのが、「ハヤシ」という料理は、「早矢仕(ハヤシ)」さんという実在の人物が作ったからという説です。
明治時代の丸善(書店・洋書店)の創業者である早矢仕 有的(はやし ゆうてき)氏が、余った牛肉を煮込んで作った料理が始まりとされ、「ハヤシさんのライス」が「ハヤシライス」と呼ばれるようになったという話です。
 マナブ
マナブえっ、料理の名前に人の名前がそのまま使われることってあるんだね!



あるよ。例えば「ベシャメルソース」も、フランスのベシャメル侯爵の名前が由来なんだよ。
実際に、早矢仕氏が福音書の普及活動の一環として炊き出しを行っていた記録もあり、この説は信ぴょう性が高いとされています。
有力説②:「ハッシュドビーフ」説(英語由来)
2つ目の説は、英語の「ハッシュドビーフ(Hashed Beef)」がなまって「ハヤシビーフ」になったというもの。
「ハッシュド(細切れ)」+「ビーフ(牛肉)」=細切れの牛肉を使った料理、という意味から来ていて、それが日本風に変化したというわけです。
この説もまた理にかなっており、特にホテルやレストランなどで出される本格派ハヤシライスは、ハッシュドビーフに近い作り方をしていることが多いです。
有力説③:「早く作れるライス」説(俗説)
ちょっとユニークな俗説として、「ハヤシ=早い」「ライス=ごはん」→“早く出せるライス”だから「ハヤシライス」という語呂合わせ説も存在します。



ちょっとそれは強引じゃない…?



うん、これはジョークや都市伝説に近いかな。でも、言葉の由来って時々こういう面白い話が混ざってるのも魅力のひとつだね。
ハヤシライスとビーフシチューの違いとは?
見た目や材料が似ていることから、「ハヤシライスとビーフシチューはどう違うの?」と疑問に思う人も多いはず。以下に代表的な違いをまとめました。
| 項目 | ハヤシライス | ビーフシチュー |
|---|---|---|
| 主な具材 | 牛肉、玉ねぎ、マッシュルーム | 牛肉、人参、じゃがいも、玉ねぎ |
| ソースの味 | デミグラス+トマトの酸味と甘み | 赤ワインとデミグラスベースでコク深い |
| 食べ方 | ごはんにかけて食べる | パンやバゲットと一緒に食べるのが主流 |
| 調理時間 | 比的短め(煮込みすぎない) | 長時間煮込むことが多い |



確かに、ハヤシライスはサッと作れてご飯と合うけど、ビーフシチューってお店でしか食べないイメージかも。



ビーフシチューは煮込み時間が長くて手間がかかるから、特別な料理って感じだよね。でもどちらもデミグラス系で、派生関係にあるともいえるよ。
豆知識:ハヤシライスのご飯、実はバターライスにすると格上げ!
普通の白ご飯でもおいしいハヤシライスですが、バターライスやサフランライスと組み合わせると、洋食屋風の仕上がりになります。バターで炒めたご飯に塩と少しのパセリを加えるだけで、おもてなし料理にも!
まとめ
・ハヤシライスの「ハヤシ」は、早矢仕 有的(はやし ゆうてき)という人物名に由来する説が有力!
・「ハッシュドビーフ説」や「語呂合わせ説」など、複数の説が存在する
・ビーフシチューとは具材・調理法・食べ方に違いがある
次にハヤシライスを食べるときは、名前の由来やビーフシチューとの違いを思い出しながら、ちょっとした“食の旅”を楽しんでみてくださいね。