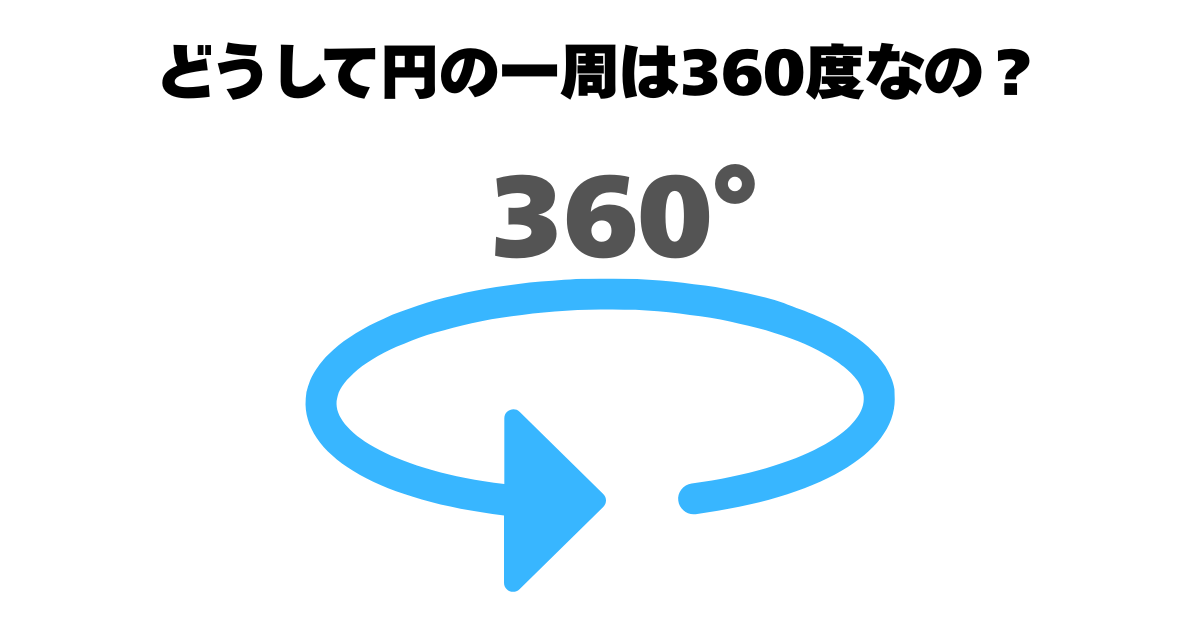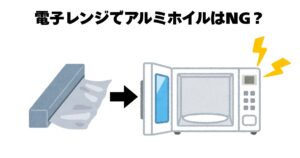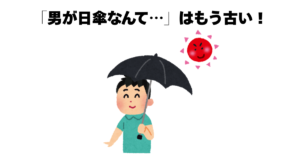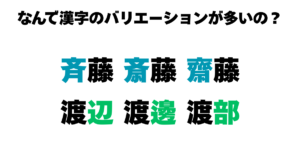「どうして円の一周は360度なの?」
そう聞かれて即答できる人は少ないかもしれません。しかし、この「360度」という数字には、古代の知恵と天文学、そして計算のしやすさという合理的な理由が隠されています。
今回は、私たちの身近な「円」と「角度」の不思議な関係について、深掘りしていきましょう!
この雑学を要約すると
- 円が360度なのは、古代バビロニアの60進法と1年=360日という観測がもとになっている
- 360は分割しやすい便利な数で、現代の時間や角度単位に影響を与えている
- 実は360度以外にも、ラジアンやグラードといった角度の表現方法がある
円が360度になった歴史的背景
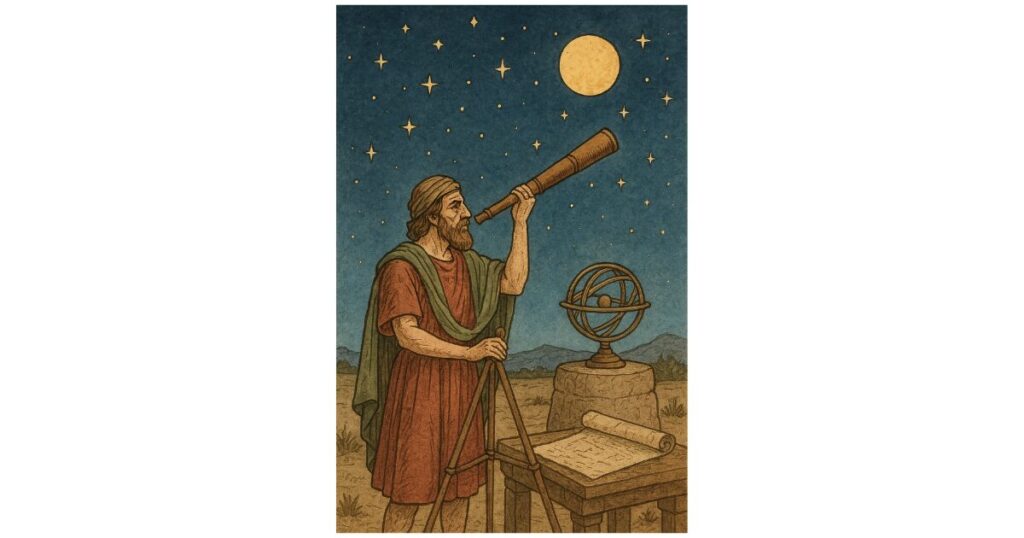
私たちが「円の一周=360度」と習うのは当たり前ですが、これは自然界の法則ではありません。人間が決めた「ルール」なんです。
そのルーツは、古代バビロニア文明にまでさかのぼります。彼らは60進法という独特の数の数え方をしていました。私たちの普段使う10進法(1〜10で数える)とは異なり、60を基準にして数を扱っていたのです。
この60進法を用いた彼らは、太陽の動きや星の位置から「1年=およそ360日」とざっくり捉えていました。
そこから「1年の動き=円の一周=360」と結びつけたと考えられています。
 マナブ
マナブえ!?円が360度なのって、科学的な理由じゃなくて、人間が勝手に決めたことだったんだ!?



そうなのよ。古代の人たちは、太陽の動きから「1年=約360日」と考えて、それを円の角度に当てはめたの。今のカレンダーとは少し違うけど、とても賢い発想だったのよね。
なぜ「360」が選ばれた?
単に「1年が360日だから」だけではありません。実は360という数字の使いやすさにも理由があります。
▼ 360は割り切れる数が多い!
360はとにかく約数が多いことで知られています。
| 割り切れる数 | 合計 |
|---|---|
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12… | 24個以上! |
つまり、360という数は分割にとても便利なんです。
たとえば、時計の分(60分)も、360度の一部であり、6度×60で割り切れるようになっています。建築や機械設計、天文学でも非常に都合が良い数なんですね。
現代でも残る60進法の名残
現代でも、私たちの生活の中には60進法の影響が残っています。
- 1分=60秒、1時間=60分
- 円の一周=360度
- 緯度・経度=60分の単位で表現
- 時計の針の動き(6度×60分=360度)



そういえば、1分が60秒なのも不思議だったけど…もしかして同じ理由?



そのとおりよ!時間の単位にもバビロニアの60進法の名残があるの。数字の分割がしやすいから、今でも使われているのよ。
豆知識:実は「円の角度」は他にもある!
- ラジアン(rad):数学や物理で使われる角度の単位。円周の長さを使って定義されており、「360度=2πラジアン」となります。
- グラード(gon):フランスなどで採用された角度単位。「1周=400グラード」とし、直角を100にするという考え方。
このように、360度以外にも「角度の考え方」は複数あるのです。私たちが360度に慣れているのは、あくまで文化的背景によるものなのです。
まとめ
- 円が360度なのは、古代バビロニアの60進法と1年=360日という観測がもとになっている。
- 360は分割しやすい便利な数で、現代の時間や角度単位に影響を与えている。
- 実は360度以外にも、ラジアンやグラードといった角度の表現方法が存在している。
「円はなぜ360度?」という素朴な疑問の裏には、人類の長い歴史と知恵が詰まっていました。何気なく使っている数字の背後には、古代の星空を見上げた人々の観測と工夫がある―――そんなことを思い出すと、数字もぐっと身近に感じられますね。
次に時計を見るときは、「あ、この60も昔の名残かも」と思い出してみてください!