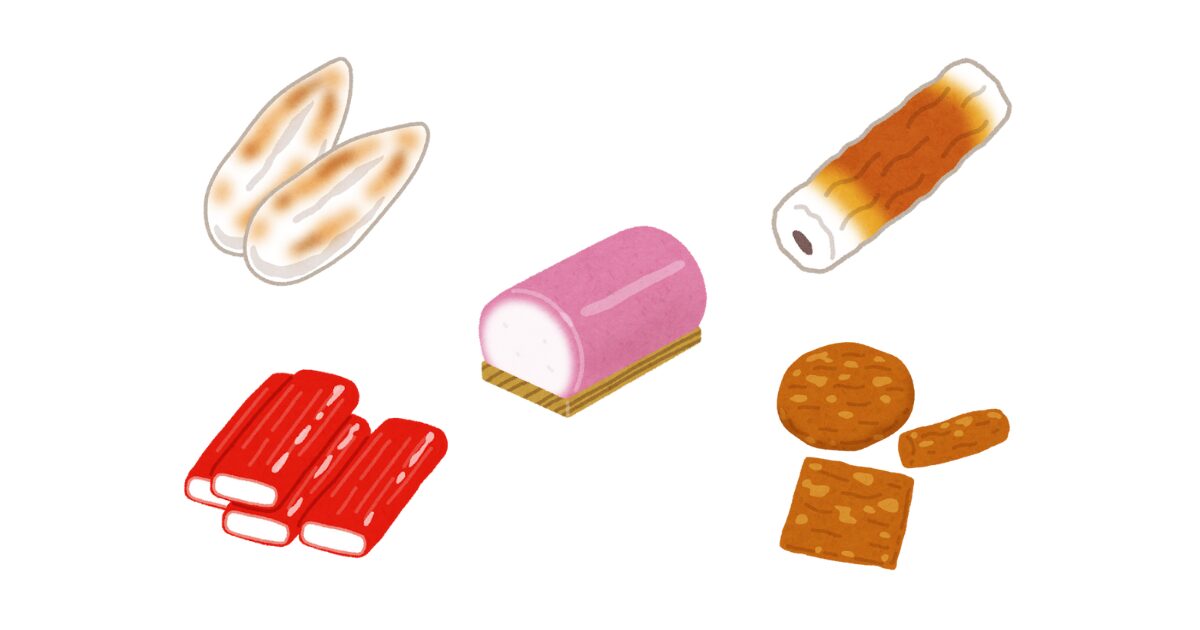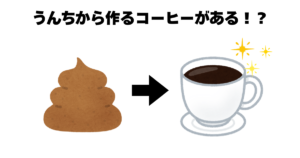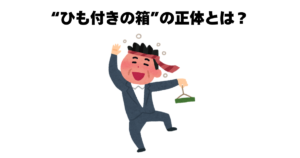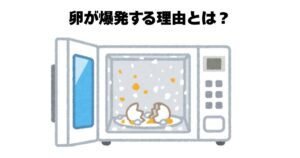魚のすり身を使った「練り物」。かまぼこ、ちくわ、さつま揚げなど、食卓でもおでんでも定番の存在です。でも、ふと気になりませんか?
「これって、何の魚でできてるの?」
今回は、意外と知られていない「魚の練り物の原料」について、わかりやすく解説します!
この雑学を要約すると
- 練り物にはスケトウダラを中心に、エソやイトヨリなどさまざまな魚が使われている
- 味や食感は魚の種類・配合・加工方法によって変わる
- 地域ごとの練り物には独自の魚や味付けがあり、食べ比べも楽しい!
練り物に使われる魚って?
練り物の主な原材料は「魚のすり身」。このすり身に塩や調味料を加えて、加熱・成型したものが練り物です。
使用される魚にはいくつか種類があり、主に以下のようなものが使われます。
よく使われる魚の例

スケトウダラ(スケソウダラ)
⇒ 練り物の代表格。クセが少なく、弾力のあるすり身が作れる。
ハモ、トビウオなど地域によって多様な魚種
⇒ 地方によっては地元の魚を使って練り物が作られている。
イトヨリダイ
⇒ 上品な白身魚で、風味が良い。高級かまぼこに使われることも。
グチ(イシモチ)
⇒ 弾力があり、かまぼこの食感に向いている。
エソ
⇒ 小骨が多く生で食べにくいため、練り物として有効活用。
 マナブ
マナブかまぼこっていつも食べてるけど、あれって一種類の魚でできてるの?



いい質問ね!実はかまぼこにはスケトウダラって魚がよく使われるの。でも、製品によってはいろんな魚をブレンドして使っているのよ。



ブレンド!?まるでコーヒーみたい!



そうね。魚の種類や配合のバランスによって、食感や味、香りが変わるから、練り物職人の腕の見せ所ってわけ。
どうしてこれらの魚が使われるの?
練り物に向いている魚には共通点があります。
- 白身魚でクセが少ない
- 筋肉質で弾力のあるすり身ができる
- 加熱しても固くなりにくい
- 大量に漁獲でき、安定供給が可能
例えば、スケトウダラは冷凍しても品質が落ちにくく、世界中で大量に漁獲されているため、加工食品に最適とされています。
地域限定!ご当地練り物の面白さ
練り物は地方によっても特徴があります。
例えば…
- 鹿児島県の「さつま揚げ」:甘めの味付けとふんわりした食感が特徴。地魚を使うことも。
- 山口県の「ちくわ」:エソなど地元の魚を使い、炭火で焼いて香ばしく仕上げる。
- 愛媛県の「じゃこ天」:小魚を骨ごとすり潰して揚げた、カルシウムたっぷりの逸品。
豆知識:
練り物に使われる「すり身」は「冷凍すり身」として世界中に輸出されていて、日本以外でもアジア各国の練り物料理に使われています。
まとめ
・練り物にはスケトウダラを中心に、エソやイトヨリなどさまざまな魚が使われている
・味や食感は魚の種類・配合・加工方法によって変わる
・地域ごとの練り物には独自の魚や味付けがあり、食べ比べも楽しい!
普段何気なく食べている練り物も、「何の魚からできているんだろう?」と考えて食べると味の違いがわかってくるかもしれないですね!