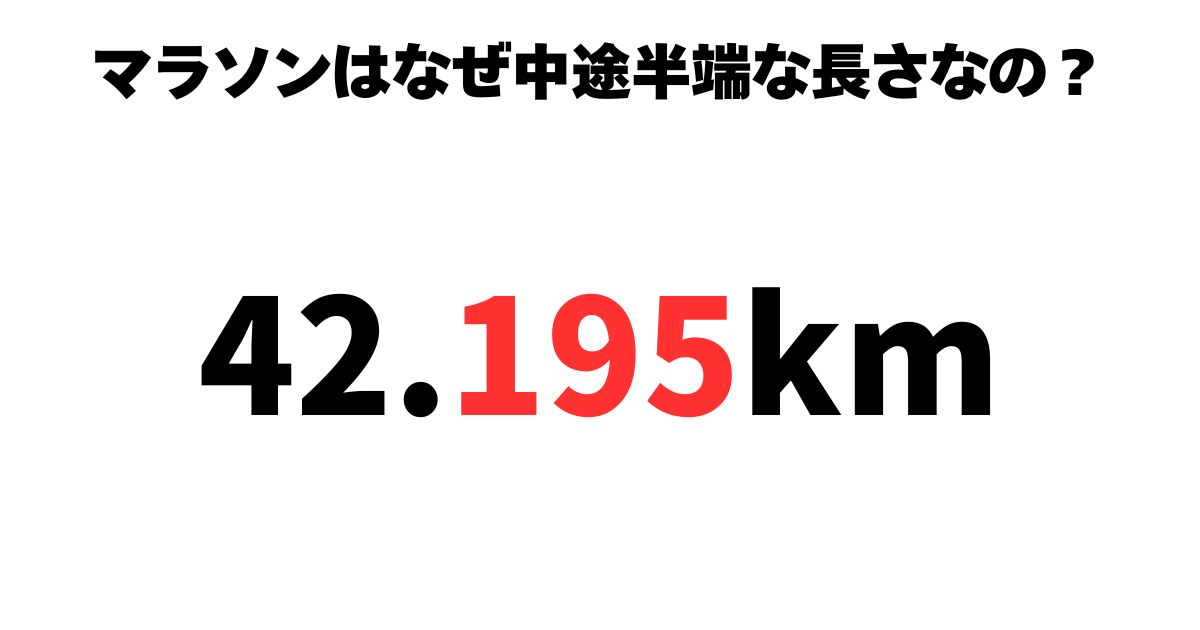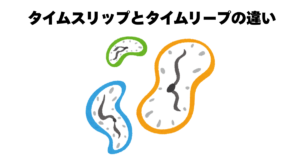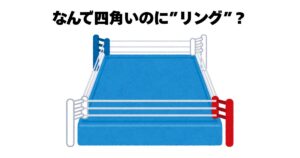「フルマラソン=42.195km」
誰もが知るこの数字、でも「なぜピッタリ40kmでも42kmでもないの?」と不思議に思ったことはありませんか?
実はこの“195mの謎”には、オリンピックと王室のワガママ(?)が深く関わっていたのです。
この雑学を要約すると
- フルマラソンの起源はギリシャのマラトンの戦いで、当初は約40kmだった
- 1908年ロンドン大会で王室の都合により42.195kmに設定され、それが正式距離に
- ペースメーカーの導入など、現代でも進化を続ける競技となっている
マラソンの起源は古代ギリシャにあった

物語の始まりは紀元前490年のマラトンの戦い。
ギリシャ軍の兵士・フィディッピデスが、ペルシャ軍を破った勝利の知らせを伝えるために、マラトンからアテネまで約40kmを走り抜けたとされています。
彼はその後、「喜びを伝え終えた瞬間に息絶えた」と伝説に残りました。
このエピソードが後のマラソン競技の由来となったのです。
つまり、本来のマラソン距離は「約40km」だったというわけです。
 マナブ
マナブへぇ〜、最初から42.195kmだったわけじゃないんだね!



そうなの。実は“195m”が足されたのは、あるオリンピックの“特別事情”があったからなんだよ。
距離が決まっていなかった初期のマラソン
実は、第1回アテネ大会(1896年)では約40km、パリ大会(1900年)は約40.26km、セントルイス大会(1904年)では約40kmと、
大会ごとに距離が微妙に違っていました。
ルールが統一されていなかったため、「マラソン=おおよそ40km」という曖昧な扱いだったのです。
42.195kmになったきっかけ:ロンドンオリンピックの「王室のわがまま」


1908年のロンドンオリンピック。
このとき、スタート地点はウィンザー城の庭、ゴールはロンドンのオリンピック・スタジアムの王族席前に設定されました。
このコースを測った結果が―――42.195km!
つまり、「スタートを王室の敷地に」「ゴールは王族が観覧できる席の前に」という王室の希望が生んだ距離だったのです。
これがそのまま国際的に定着し、1921年に正式にマラソン=42.195kmと決まりました。



たった195mって、王族の“座ってる場所”までだったの!?



そう。だから“人類の限界を超える競技”が、実は“王室の都合”でできたっていうのが面白いよね。
マラソンの「ペースメーカー」って何者?
マラソン中継でよく聞く「ペースメーカー」。
これは選手が一定のペースで走るのを助ける役割を持つ人のことです。
彼らはゼッケンをつけており、途中でレースを離脱するのが基本ですが、一定のスピードを保つことで世界記録や好タイムを狙いやすくするんです。
ちょっと役立つマラソン豆知識
- 世界最古の市民マラソン大会は「ボストンマラソン」(1897年〜現在まで継続)。
- 日本の「箱根駅伝」は1区間あたり約20kmで、ほぼ“ハーフマラソン”相当。
- 一般人の完走率は約90%。初心者でも半年あれば完走が目指せます!
まとめ
- フルマラソンの起源はギリシャのマラトンの戦いで、当初は約40kmだった。
- 1908年ロンドン大会で王室の都合により42.195kmに設定され、それが正式距離に。
- ペースメーカーの導入など、現代でも進化を続ける競技となっている。
ただの「42.195km」という数字も、こうした歴史を知ると深みが出ます。
マラソンはただのスポーツではなく、古代ギリシャの伝説と英国王室の物語が融合した“歴史の結晶”なんですね。