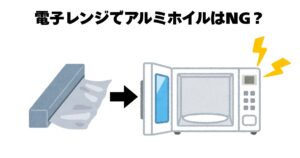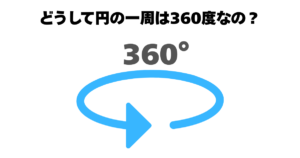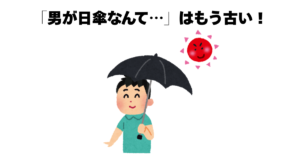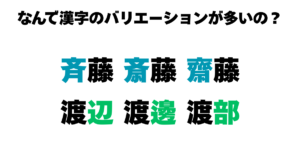「物価ばかり上がって、給料はちっとも増えない」
「昔みたいにストライキとか起きれば、少しは変わるんじゃないの?」
そんな疑問を持つあなたへ。
本記事では、日本で給料が上がらない理由と、ストライキがなぜ衰退したのかを解説し、いま労働者ができることを考えていきます。
この雑学を要約すると
- 価が上がっても給料が上がらない背景には、企業体質・雇用構造・労組の弱体化がある
- ストライキが減ったのは、非正規雇用の増加、社会的プレッシャー、制度的制限が原因
- 声を上げる方法は変化している。SNS、副業、法知識の活用で、現代の労働者にもできるアクションがある
物価は上がっているのに、給料が上がらない理由
日本ではここ数年、食料品、電気代、ガソリン代など、あらゆる生活コストが上がっています。
これはエネルギー価格の高騰や円安など、外部要因が大きな影響を及ぼしています。
しかし、それに見合った給料の上昇はほとんど見られません。理由としては以下の通りです。
企業の内部留保重視
多くの日本企業は利益を社員に還元するより、貯め込む傾向が強く、いったん上げたら下げにくい人件費を増やすことに消極的です。
非正規雇用の増加
アルバイトや派遣社員など、待遇の低い働き方が増えたことで、全体の給与水準が上がりにくくなっています。
年功序列と終身雇用
若手の給料を上げにくい構造が、企業の中に根付いたままです。
 マナブ
マナブ物価はどんどん上がってるのに、どうして給料は増えないんだろう?



それはね、日本の企業文化が“貯め込む体質”になってしまっているからよ。将来のリスクに備えるばかりで、今の労働者に還元しようとしないの。



昔はストライキとかしてたよね?今は誰も立ち上がらないの?



いいところに気づいたわね。でも、今はストライキをしにくい理由がたくさんあるの。
昔のようなストライキが少なくなった理由


かつての日本では、鉄道、教師、運輸業界などで大規模なストライキが頻発していました。
しかし現在では、ほとんど見られなくなりました。その背景には以下のような理由があります:
労働組合の弱体化
かつては3割以上が労組に加入していましたが、今や10%以下。団結力のある交渉ができなくなっています。
非正規雇用の拡大
解雇のリスクが大きい非正規労働者はストライキに参加しづらく、会社側が強気な姿勢をとっていることも現実。
社会的なプレッシャー
「ストをして迷惑をかける=悪」という空気が強く、声を上げることに躊躇する人が多いです。
ストライキは合法でも、制限が多い
日本では法律上ストライキは認められていますが、公共性の高い仕事では制限が多く、実行には高いハードルがあります。
では、労働者はどうすればいいのか?
1. SNSや署名活動で声を上げる
今の時代、組合に所属せずとも、SNSで問題提起したり、オンライン署名で社会に訴える方法があります。
2. 副業やスキルアップで自衛する
給料が上がらないなら、自分で収入源を増やすしかありません。スキルを磨いて、転職や副業で選択肢を広げましょう。
3. 労働法に詳しくなる
自分の権利を知れば、違法な労働環境に立ち向かえるようになります。労基法やパワハラ防止法などの基礎知識は武器になります。
豆知識:ストライキは「争議行為」と呼ばれる合法な手段
労働者が団体で仕事を停止して交渉する行為=ストライキは、日本でも労働組合法で認められています。
ただし、「職場に損害を与える」「社会に迷惑をかける」などの理由で批判されやすくなっているのが実情です。
まとめ
・物価が上がっても給料が上がらない背景には、企業体質・雇用構造・労組の弱体化がある。
・ストライキが減ったのは、非正規雇用の増加、社会的プレッシャー、制度的制限が原因。
・声を上げる方法は変化している。SNS、副業、法知識の活用で、現代の労働者にもできるアクションがある。
今の社会では、ただ我慢して働き続けるだけでは搾取されかねません。
「声を上げること」「備えること」こそ、これからの労働者に必要な力です。
あなたは沈黙しますか?それとも、行動しますか?