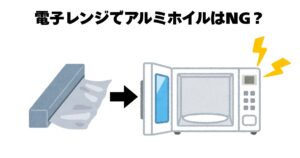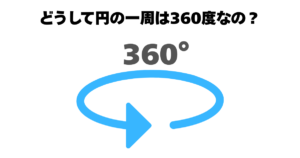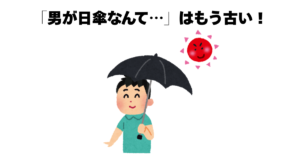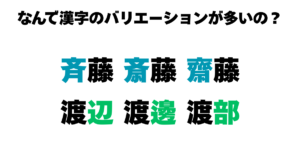「青森の夏祭り」と聞くと、「ねぶた祭り」や「ねぷた祭り」が思い浮かびますよね。でも、同じような名前なのに、ねぶたとねぷたって何が違うの?と疑問に思ったことはありませんか?
この記事では、「ねぶた」と「ねぷた」の違いを、初心者にもわかりやすく徹底解説します。地域や歴史、見た目の特徴までしっかり押さえていきましょう!
この雑学を要約すると
- 「ねぶた」は青森市、「ねぷた」は弘前市で開催される別の祭り
- 灯籠の形状と雰囲気が大きく異なり、それぞれの地域文化が反映されている
- どちらも「眠り流し」から発展した共通の起源を持っている
そもそも「ねぶた」と「ねぷた」って何?

まず最初に、それぞれの祭りの概要を簡単に押さえておきましょう。
ねぶた祭り:青森市で開催される大規模な夏祭り。立体的で迫力ある山車灯籠(だしとうろう)が特徴。
ねぷた祭り:弘前市を中心に開催される夏祭り。扇形の灯籠が特徴で、どこか静かな趣があります。
いずれも8月初旬の約1週間開催されます。
地域による違いが一番のポイント!

「ねぶた」は青森市、「ねぷた」は弘前市。
このように、地域によって名前が異なるところが大きなポイント。また、同じ青森県内でも掛け声やスタイルが変わるのが面白いところ。
 マナブ
マナブねぶたとねぷた、名前が似すぎてややこしいよ〜。どっちも灯籠を出すんだよね?



そうね。でも山車灯籠の形が大きく違うのよ。ねぶたは立体的で、戦国武将や鬼などの迫力ある造形が特徴。ねぷたは扇形で、静けさと美しさが際立つわ。



なるほど!表現したいものが違うんだ。ねぶたは「動」、ねぷたは「静」って感じかな。



そんな感じ。実は、同じ「眠り流し」が由来でも、地域の文化が表現に影響しているの。
起源は同じ!?「眠り流し」の風習から
実はどちらも、「眠気(ねぶけ)」を流す風習から生まれたとされています。田んぼ仕事で溜まった疲れや眠気を、夏祭りの灯籠に乗せて川へ流し、厄除け・無病息災を祈願していたんですね。
この風習が、後に豪華な山車灯籠を使った祭りに発展していったというわけです。
見た目の違いにも注目!
| 比較項目 | ねぶた | ねぷた |
|---|---|---|
| 地域 | 青森市 | 弘前市 |
| 山車灯籠の形 | 人形型の立体造形 | 扇型の平面造形 |
| 雰囲気 | 派手・勇壮 | 落ち着いた美しさ |
| 掛け声 | 「ラッセラー!」 | 「ヤーヤドー!」 |
なぜ武将のデザインなのか?
ねぶたやねぷたの原型は「眠り流し(ねぶけながし)」という風習です。
この行事には、災厄・悪霊を追い払うという意味が込められていました。
そのため、勇ましい顔や恐ろしい表情の武将や鬼などのデザインが多用されたのです。
強い存在を描くことで、「災いに負けないぞ!」という魔除け・祈願の象徴となりました。
ちょっと得する豆知識!
- 「ねぶた」と「ねぷた」は使われている漢字は同じ「侫武多」
- 弘前の「ねぷた」の方が観光客が少なめで、ゆったり楽しめる
- 青森市では「跳人(はねと)」と呼ばれる踊り手も人気の存在!
まとめ
・「ねぶた」は青森市、「ねぷた」は弘前市で開催される別の祭り
・灯籠の形状と雰囲気が大きく異なり、それぞれの地域文化が反映されている
・どちらも「眠り流し」から発展した共通の起源を持っている
「ねぶた」と「ねぷた」、似ているようで違う奥が深い夏祭り。それぞれの違いを知ると、どちらも実際に訪れたくなりますよね。もし次の夏、青森方面に旅行を考えているなら、どちらも同じ時期に1週間開催されているので、両方の祭りを見比べてみるのもおすすめです!