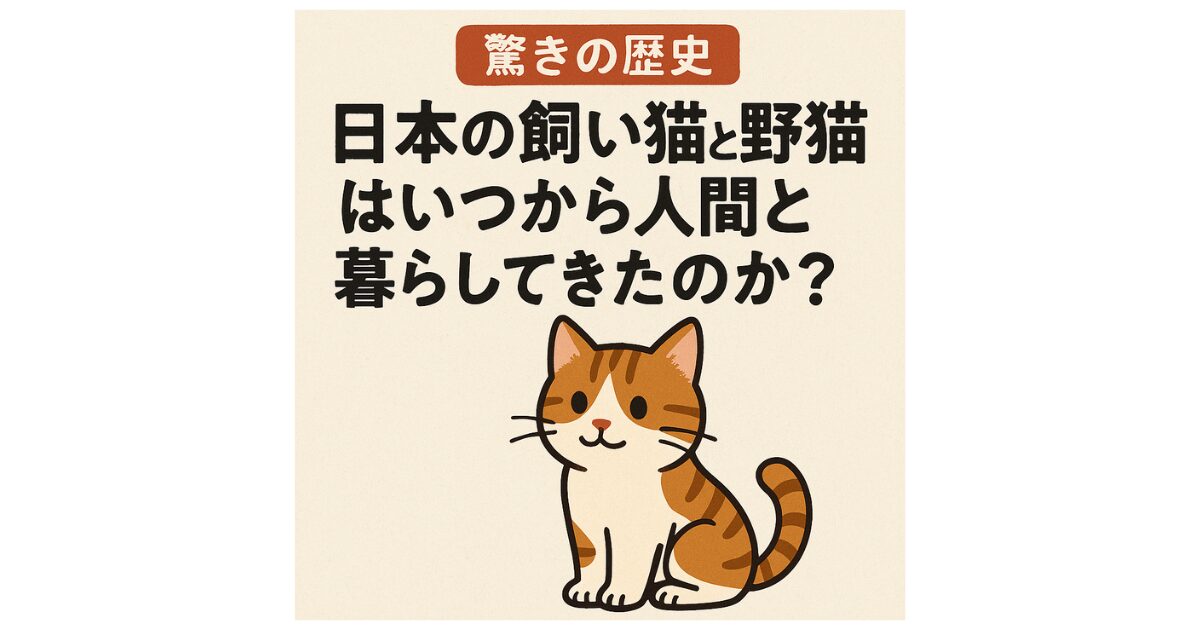「猫は気まぐれ」と言われますが、そんな猫たちが人間と共に暮らすようになったのは、いつからなのでしょうか?
日本における飼い猫の歴史や、野良猫との関係の変遷には、意外なドラマが隠されています。今回は、猫と日本人との歴史的なつながりを紐解いていきましょう!
この雑学を要約すると
- 日本に猫がやってきたのは奈良時代。経典を守るために輸入された。
- 平安時代には貴族に愛され、江戸時代に庶民の間でも一般的に。野良猫の増加もこの時期から。
- 現代では完全室内飼いが主流に。地域猫活動など野良猫との共生も課題。
日本に猫がやってきたのはいつ?
猫はもともと日本固有の動物ではありません。
日本に猫が初めてやってきたのは、古代・奈良時代(710〜794年)ごろだと考えられています。
当時、仏教の経典や文書を守るために、ネズミから守る存在として中国から船で運ばれてきたという記録があります。つまり、猫は最初から「守り神」のような役割で迎え入れられたのです。
 知恵の妖精ミネル
知恵の妖精ミネル奈良時代に猫がいた証拠として、写経をしていた僧侶の日記に“猫がネズミを捕った”という記述が残っているのよ。日本最古の“猫の記録”ね。



へぇ!昔から猫って文書の守護者だったんだ…今じゃパソコンのキーボードの上に乗って邪魔してくる可愛いやつだけど(笑)
平安時代〜江戸時代:猫が“愛玩動物”へと変化
平安時代になると、猫は貴族の間でペットとして飼われる存在に変化していきます。
『枕草子』や『源氏物語』などの古典文学にも、猫の登場シーンが見られます。
一方、江戸時代になると庶民にも猫が広まりました。この時代、猫は自由に歩き回る「放し飼い」が主流で、そこから野良猫のような存在が生まれたと考えられます。



江戸時代の浮世絵にも、猫の絵がたくさん描かれてるわよ。人々が猫と暮らす日常が垣間見えるの。



なるほど…じゃあ“野良猫”って江戸時代あたりから増えたのかも?
明治以降〜現代:ペットとしての地位が確立
明治時代には西洋文化が流入し、猫もより“ペット”として意識されるようになります。
昭和〜平成にかけては、室内飼いが徐々に広まり、今では完全室内飼いが主流です。
一方で、去勢・避妊の習慣がなかったため、野良猫も増えてしまい、近年ではその数を地域猫活動などでコントロールする動きも見られます。
役立つ豆知識:猫が好きな「またたび」、実は日本原産!
猫が大好きな「またたび」は、日本にもともと自生する植物です。
猫の嗅覚を刺激する成分が含まれていて、一種の“酔っ払ったような反応”を引き起こすことで知られています。
これは、ストレス解消やコミュニケーション促進にも効果的だといわれています。
まとめ
・日本に猫がやってきたのは奈良時代。経典を守るために輸入された。
・平安時代には貴族に愛され、江戸時代に庶民の間でも一般的に。野良猫の増加もこの時期から。
・現代では完全室内飼いが主流に。地域猫活動など野良猫との共生も課題。
猫と人間の関係は、「守る存在」から「癒しの存在」へと変化してきました。
今、あなたのそばにいる猫も、1000年以上続く人と猫の物語の“続き”を生きているのかもしれませんね。