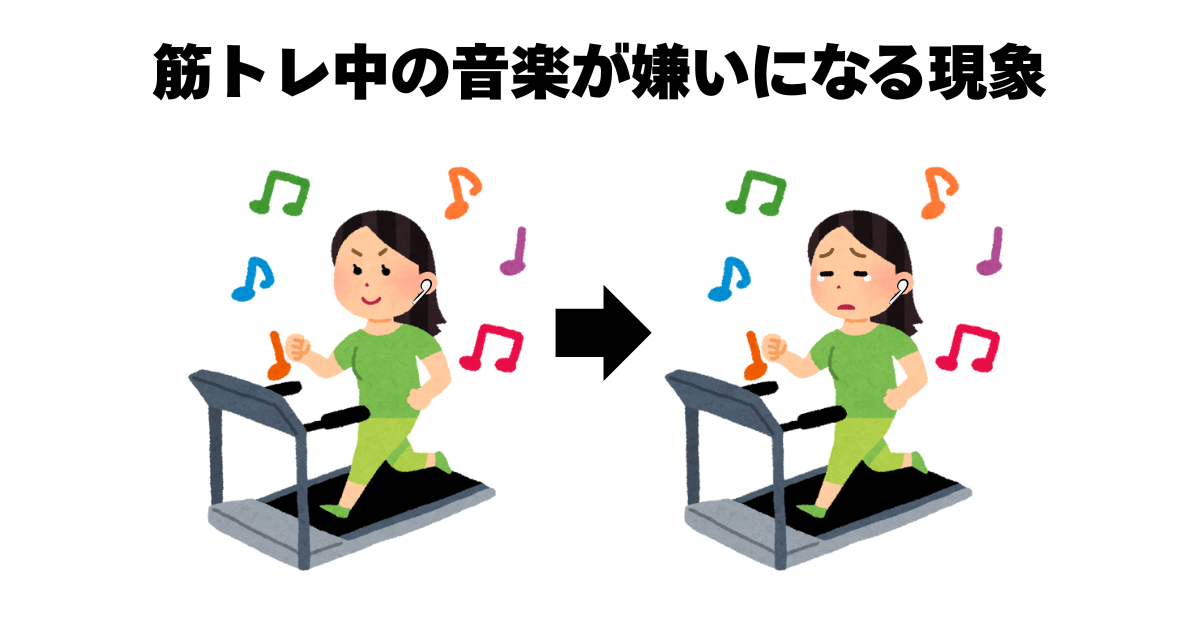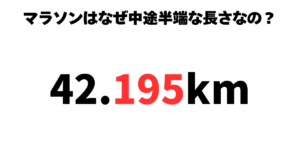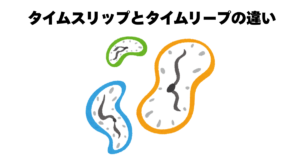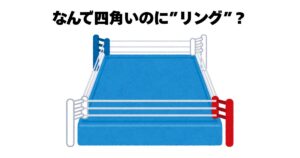「筋トレ中にノリノリで聴いてた曲が、なぜか最近聴きたくない…」
そんな経験、ありませんか?
実はこれ、心理学的にもごく自然な現象です。
この記事では、筋トレ中の音楽が好きじゃなくなる理由を、脳の仕組みや感情の動きとともに解説します。
この雑学を要約すると
- 筋トレ中に音楽が嫌いになるのは、辛い記憶と結びつく心理的影響が大きい
- 繰り返しの視聴や心境の変化で、曲の魅力が薄れることもある
- 複数の曲をローテーションすることで回避できる!
筋トレと音楽の深い関係
筋トレ中に音楽を聴くと、気分がアガってやる気もアップしますよね。
これは、音楽がドーパミンやエンドルフィンの分泌を促すことで、やる気や快感を高めてくれるため。
しかし、その「アガる音楽」が後々嫌いになってしまうケースも少なくありません。なぜなのでしょう?
原因1:キツい記憶と結びついてしまうから

筋トレ中は、身体だけでなく脳もストレス状態にあります。
筋肉の痛み、疲労、思うように成果が出ない焦り…。
それらの負の感情が音楽とセットで記憶されると、その曲を聴くたびに無意識に不快感が蘇るようになるのです。
 知恵の妖精ミネル
知恵の妖精ミネル人の脳は、音楽と感情を強く結びつけて記憶するの。辛い筋トレと一緒に聴いてた曲が、無意識に『苦しい記憶』として脳に刻まれちゃうのよ。
原因2:繰り返しすぎて“音楽疲れ”を起こす
「お気に入りの一曲をループで聴いてた」―――それ、実は音楽の味を失わせる最短ルートです。
脳は予測できる刺激には反応しにくくなるため、繰り返し聴くことで「もうドキドキしない曲」になってしまうのです。



お気に入りだから何回も聴いてたのに、なんで飽きちゃうの?



“感情の新鮮さ”が失われると、脳が刺激を感じにくくなるの。結果的に『もういいや』ってなるのよ。
原因3:自己評価の変化による“距離感”のズレ
例えば、筋トレを始めた当初は「ちょっと無理してでも気合を入れたい」と思って激しいロックやEDMを聴いていた人も、数ヶ月経って余裕が出てくると、その選曲が自分に合っていないように感じるようになることも。
人は、心境や自己イメージの変化に合わせて音楽の好みも変わるもの。
筋トレの習慣化に伴って、求める音楽の方向性も自然と変化していくのです。
対処法:音楽の“消耗”を防ぐには?
ここからは、音楽に対する嫌悪感を防ぐためのコツをいくつか紹介します。
1. 曲をローテーションする
毎回同じ曲ではなく、プレイリストを複数用意して使い分けることで“音楽疲れ”を予防しましょう。
2. BGM感覚でインストやLo-Fiも使う
言葉のある曲は感情との結びつきが強くなりやすいため、あえてLo-Fiヒップホップや環境音を使うのもおすすめ。
お気に入りの音楽はあえて聞かないという選択も有効です。
まとめ
- 筋トレ中に音楽が嫌いになるのは、辛い記憶と結びつく心理的影響が大きい。
- 繰り返しの視聴や心境の変化で、曲の魅力が薄れることもある。
- 複数の曲をローテーションすることで回避できる!
筋トレ中に聴いていた大好きな曲が、いつの間にか遠ざけたくなる…。
そんな経験をした人は少なくないと思います。
でもそれは、あなたが頑張った証拠でもあるんです。
音楽との付き合い方をちょっと工夫するだけで、筋トレも気分もまた前向きになれますよ!